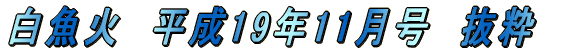盗 人 萩 安食彰彦
秋扇内ポケットより出しにけり
海風につぶやき多き稲穂かな
声零しわつと翔ちたる稲雀
新涼の烏にもある淡き影
盗人萩賓頭廬尊者眼を瞑る
宝前に新涼の風貰ひけり
社家の前影の大きな秋茄子
階に曲る畦径痩案山子
灸 花 青木華都子
乗り越して戻るひと駅蝉しぐれ
人通り途絶えし路地の灸花
蝉の殻踏み壊したる足の平
油蝉迷ひ込んだり会議中
新盆の供養の酒を廻し呑む
麦藁帽顔にうたた寝してをりし
秋暑しテントの中の診療所
涼新た塔に重ねし塔の影
新 涼 白岩敏秀
水馬水輪のなかにある日暮
蝉しぐれ一樹縛してゐたりけり
蛾をつれて西日に向ふ列車あり
花火見し夜を美しく眠りけり
今朝の秋触るるものみな鮮しき
西瓜切る等分といふ偶数値
新涼を歩けば砂の鳴りにけり
鈴虫の飼はれて鳴きぬ六校時
首 飾 坂本タカ女
向日葵の顔ちくちくと蜂ありく
天牛の麝香を放つ髭を振る
金亀子多士済済のカフェの客
朝顔やけふよき顔でありにける
学校図書室の踏台雲の峰
暑かろと言ひ熱き茶を淹れくるる
肩寄する頬よするかにダリヤ咲く
蛍火や胸に重たき首飾
一 都 忌 鈴木三都夫
風はたと死に途絶えたる砂丘かな
風止んで息のつまりし暑さかな
後ろより日傘の蔭を貰ひけり
危ふげな葉先捉へし糸とんぼ
山の蟻句帖へ許す木下かな
曝す書に侍りて一都忌なりけり
一都忌の日に日に遠く門火焚く
一都忌の床に一軸水中花 |
赤 い 月 佐藤光汀
八月十五日塩の効きたるおむすびよ
夕ながし今日月蝕の赤い月
鈴懸の葉裏を返す実なりけり
昼花火どどんと響き里祭
仰ぐもの生き生きとせる秋の蝉
小鳥来る街に夫婦のパン工房
唐 黍 鶴見一石子
阿寒湖の星美しや虫の声
爽やかに句を作るべし生くるべし
つづれさせとぎれ鳴きして夜を深め
歩に合はぬ流星矢継ぎ早に消ゆ
唐黍の百万本の平野かな
狩勝峠靴先に秋の風
登山の荷 三浦香都子
昔むかしの電信柱ぎす鳴けり
登山の荷負うて重心定まりぬ
山開き男結びに靴の紐
山清水五臓六腑を素通りす
薔薇匂ふほどの日差しとなりにけり
ふれてみたくて触れにけり京鹿子
穴まどひ 渡邉春枝
船の上に舟の積まるる晩夏かな
尾の見えて遊び足らざる穴まどひ
放牛の空をあまさず鰯雲
栗の実の落ちて馬場跡牛舎あと
樹木医の仰ぐ神木秋気満つ
ひぐらしに攻められてゐる畑仕事
蝉 の 骸 小浜史都女
草を引く軍手のままで黙祷す
蝉の骸鳴き尽したる軽さかな
盆過ぎや預りし子の爪を切る
子蟷螂見構ふることまだ知らず
鳳仙花路地抜けてまた路地となる
太陽のしろさよ野分近づきぬ
花 芒 小林梨花
中天を向きし朝顔はりつめて
石走る垂水は海へ花芒
磯鴫の吹かれ来て又吹かれ飛ぶ
故郷の味の詰まりし梨を剥く
青梨の少し黄ばみて父母の味
闇深き背山より降る虫の声
月 食 田村萠尖
かかあ天下の国に住み古り大昼寝
背高な朝顔にある明けの風
牽牛花喉の底までさらしけり
小さき花撓め蜜すふ揚羽蝶
皆既月食木槿の白き庭の闇
月食の戻りつつあり虫すだく |